はいさいぐすーよーちゅーがなびら(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
沖縄そば大好き夫婦のまいそばです。
今回は沖縄そばの起源や歴史について書いていきたいと思います。
・沖縄そばはどうやってできたの?
・いつの時代からあるの?
・何種類ぐらいあるの?
という疑問に答えていきます。
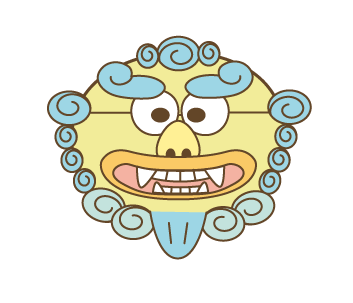
この記事は次のような方におすすめ!
・沖縄そばの歴史を知りたい。
・沖縄そばにはどんな種類があるのか知りたい。
・沖縄が好きで沖縄の食文化に興味がある。
沖縄そばの起源
明確な記録は残されていないが、1534年に琉球王の四十九日供養に「粉湯(中国語で、汁そばという意味)」を献上した。
これが宮廷料理となり、後の明治時代には裕福層に食され、明治中期頃、唐人(中国人)が那覇にそば屋を開いたことが沖縄そばのルーツとされているそうです。
現在、沖縄そばの麺は蕎麦粉を一切使っておらず、100%の小麦粉にかん水を加えて作っています。
この原料と製法から沖縄「そば」でありつつも中華麺に属するそうです。
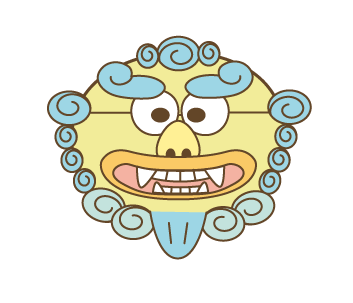
最初の沖縄そばは、しょうゆで黒い出汁の「唐人そば」というのが始まりだから、中華そばに近かったんじゃないかな。

麺も中華麺に属するし、沖縄そばはラーメンの仲間なんだね。
沖縄そばの歴史
沖縄そばの歴史は明治中期頃、唐人(中国人)が那覇に初めてそば屋を開店したのが始まりとされている。
当時は木灰を使い、麺に弾力を出していたそう。
沖縄そば の麺は小麦粉と塩、かん水で作られています。
戦前、かん水の代わりに使われていたのが木灰だそうです。
ガジュマルやデイゴなどの硬い樹木を燃やしてできたものが木灰。
この木灰を水に入れてできた上澄み(灰汁)を、かん水の代わりに使われているものが木灰そばとなるそうです。
その後、唐人のそば屋で修行した沖縄人の比嘉さんが「比嘉店」(通称「ベーラーそば」)というそば屋を開く。
両者は数年間営業合戦を繰り広げ、そばの具に薄焼き玉子を乗せるなどして工夫を凝らした比嘉さん(ベーラーそば)が勝利を収めたそうです。
明治後期には名護に初の沖縄そば屋「梅屋」などもできてきた。
大正に入ると続々とお店が登場し沖縄そばも様変わりしてくる。
この頃の具のメインは一口大の赤肉とネギだったが、那覇市の辻に開業した「ウシンマーそば」は、かまぼことショウガを乗せ、八重山のピパーチ(長こしょう)を香辛料に使い人気を博した。
始まりは醤油ベースの黒い出汁
豚骨とカツオ節の合わせ出汁に醤油を加え、塩で味を整えたのが沖縄そばの始まりの出汁。
現在主流になっている透明な出汁とは大きく違っているのだが、そのきっかけになったのが1918年那覇市首里に開店した「ゆたか屋」。
これまでの醤油ベースの味付けを塩ベースに変えただけだったのだが、当時の他店ではその謎が解けず、白い醤油を使っているだとか色々な憶測が飛び交ったそう。
最終的には各店とも醤油の量を減らし、現在の透明な出汁に落ち着いたそうです。
さらに、現在に至るまで長年沖縄そばのお供として食されてきた紅しょうがですが、この紅しょうがを始めて沖縄そばに乗せたのもこの「ゆたか屋」なんだそうです。
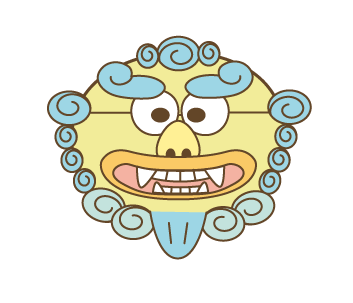
1918年頃に開業した「ゆたか屋」さんの作った沖縄そばが100年以上も受け継がれているとは驚きです。
麺造りに欠かせない木灰が入手困難に
第二次世界大戦の沖縄戦で、それまで創意工夫がなされた各地の名物そば屋も一瞬にしてすべてが破壊されてしまった。
その後、終戦した沖縄でいち早く復興を遂げたのが戦前人気の高かった名物そば屋。
そして更に、新たにお店を構える人が急増したそう。
戦争で夫を亡くした女性が生活のために沖縄そば屋を開店させるケースが多いのが、この時代の特徴らしいです。

昔の女性はほんとたくましい。尊敬するね。
1960年代頃になってくると麺造りに欠かせない木灰の入手が困難になり、それまで老舗と呼ばれていた店舗が次々と閉店していった。
この頃から、木灰に変わってかん水が使われるようになり製麺所が増えてくる。
「本場・沖縄そば」が特殊名称として登録許可
沖縄が本土復帰を果たした1970年代になってくると沖縄そばも様変わりする。
名護市に登場した「ソーキそば」。
当時、甘辛く煮込んだソーキをそばの上に乗せるのはとても画期的で、これまでの沖縄そばの概念を大きく変えるきっかけになった。
今や沖縄そばと聞いて思い浮かべる人がいるほど定番になっている「ソーキそば」だが、始めて登場したのは1975年のこと。
翌年、蕎麦粉を一切使用しない沖縄そばに「そば」の表示は規約違反というクレームが、設立したばかりの沖縄製麺協同組合に入り、歴史ある呼称を存続しようと行政への訴えを3年間続けた結果「本場・沖縄そば」という名称が正式に認可されたそうです。
この認可された10月17日を記念として「沖縄そばの日」と定め、その後様々なイベントが開催されるようになる。
1980年代になると、駐車場完備の大型沖縄そば屋が増加していき、様々な具材がそばの上に乗る多種多様な沖縄そばが生まれていった。
そして現在、沖縄の県民食として愛され1日あたりの消費量は15万~20万食にまでのぼるという。
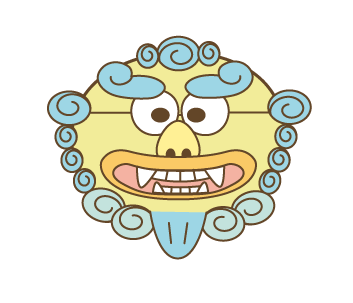
改めて沖縄そばの事を知ると、こんなにも深い歴史があったんだなーって思いました。
歴史を知って沖縄そばを食べるとまた違った味わいを感じそうですよね。

ますます沖縄そばが好きになってきたよ。
地域による沖縄そばの麺の特徴
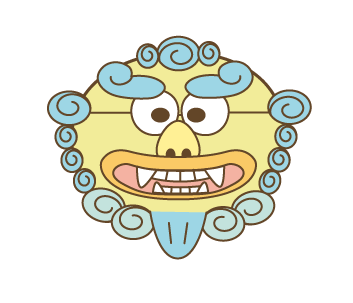
実は、同じ沖縄そばでも地域によって麺の形状や特徴が違うんです。
ここでは、各地域の麺の特徴について書いていきます。
固めの平麺
帯のような平たい麺。
沖縄本島の北部(主に名護)で好まれていて、少しもちっとした食感。
沖縄そばの中では一番固くて食べ応えのある麺です。
中細ちぢれ平麺
ちぢれた形状が特徴的で、出汁によく絡みます。
那覇を中心とした南部で好まれ食されていて一般的な沖縄そばの麺です。
この麺を扱っている沖縄そば屋が多いという印象。
丸麺
丸麺は、主に離島(石垣島等)で好まれ食されています。
他の麺よりもコシがあるのが特徴で湯通しも一番早くツルッとした食感。

最近は、麺にゴーヤーやフーチバー(よもぎ)、もずく等を練り込んでいたり、生麺や全粒粉など麺に特徴を出す沖縄そば屋も増えてきているよ。
沖縄そば歴史まとめ
今回は、沖縄そばの歴史を紹介しました。
今回の記事をおさらいすると次の通りです。
・明治中期、唐人が那覇にそば屋を開いたことが沖縄そばの始まり。
・名護に初のそば屋ができる。
・「ゆたか屋」が塩味ベースの透明な出汁を初めて提供。後の主流に。
・戦争で名物の沖縄そば屋の建物が破壊される。
・終戦後、名物そば屋が営業を再開。
・木灰の代わりに、かん水が使われるようになる。
・名護に「ソーキそば」が登場。
・「本場沖縄そば」が特殊名称として登録許可される。
・10月17日を「沖縄そばの日」と認定。
・沖縄そばの消費量が1日あたり15万~20万食となる。
いかがでしたでしょうか?
沖縄そばの歴史を知ることで、更に『沖縄』や『沖縄そば』のことに興味を持って頂けたと思います。
今後、沖縄そばを食するときの一助になれば幸いです。
以上、最後まで記事を読んで頂きありがとうございました。

